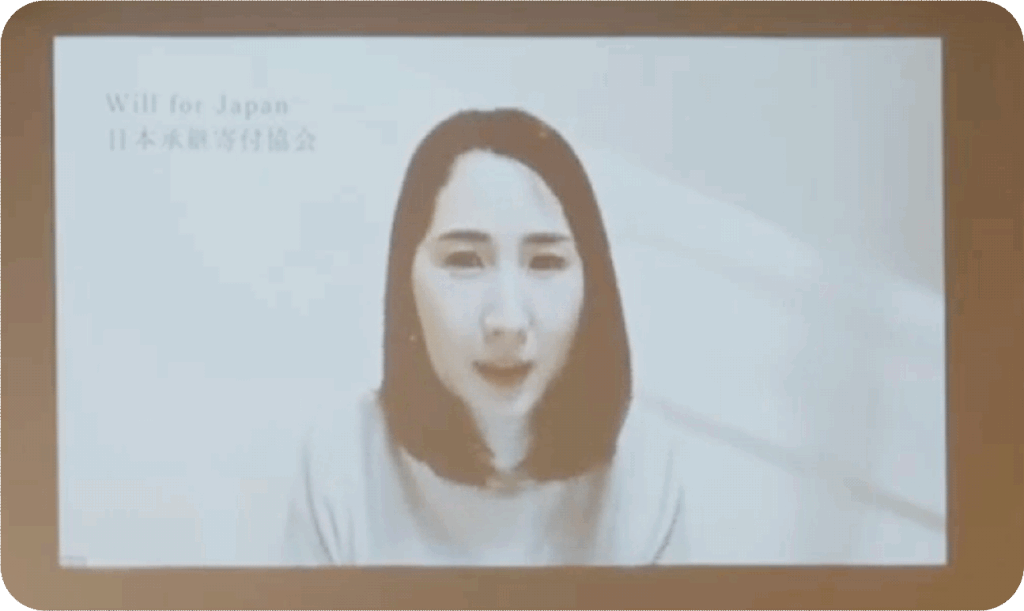Talk-Session vol.3「食で創る自分らしさ」
「高齢者の食支援」が持つ可能性
──自分らしく生き続ける社会の創生
登壇者プロフィール

株式会社オフィス・フェーヴ 代表取締役
並木麻輝子 様
パリの料理学校ル・コルドン・ブルーの製菓・料理上級課程修了(グラン・ディプロム取得)。約30年にわたり各国各地で料理・菓子を取材。専門誌、書籍、雑誌、ガイドブックなどで執筆するほか、大学、専門学校などで食文化の講義を行う。コメンテーター、食品企業アドバイザー、ラジオ、講演などの活動も行う。

特定医療法人研精会 食支援プロジェクト推進本部長
芳村直美 様
2018年に特定医療法人研精会に入職。「急性期の続きの看護がしたい」という思いから研精会で食支援プロジェクトをスタート。精神障がい・認知症・脳卒中・誤嚥性肺炎などと向き合い、支援を続けている。日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士。

株式会社プロヴィンチア 代表取締役
古屋浩 様
2012 年に山梨県甲府市朝日町で「葡萄屋 kofu」をオープン。「葡萄屋Kofu」および「葡萄屋kofuハナテラスcafé」を運営するほか、多くの飲食店のコンサルティングにも携わる。果物の魅力を引き出したスイーツに定評があり、「葡萄屋Kofu」のレーズンサンド、「葡萄屋kofuハナテラスcafé」の季節の果物のパフェで全国的人気を誇る。
セッションの様子
「食支援」は栄養補給ではない──高齢者の生きがいを支える仕組み
「食はただの栄養補給ではなく、その人らしさを形作るもの」——このメッセージが、今回のトークセッションの中心にありました。人生100年時代、食の役割は「生きるために食べる」から「自分らしさを表現する」へとシフトしています。
今回は、3名の専門家が登壇し、高齢社会における「食支援」のあり方、新たなビジネスチャンス、そしてシニア世代が豊かに生きるための視点について議論を交わしました。
東京都調布市を拠点に、「つなぐ、ひろがる、つづく」を理念医療と福祉を融合したサービスを提供する特定医療法人研精会の芳村直美(よしむら なおみ)氏は、2018年頃は貧困層の子供が主な対象だった「食支援」という言葉が現在では高齢者にも持ち込まれたことを伝え、高齢者の食に関する支援は、これまで「嚥下(えんげ)しやすい」「高栄養」といった視点で語られることが多く、「おいしさ」「楽しさ」「社会とのつながり」といった要素が軽視されてきたと指摘しました。
芳村氏は、高齢者の健康状態と要介護状態の狭間にある「フレイル(虚弱)」に焦点を当て、食支援の重要性を以下のように説明しました。
● 年齢が上がるにつれ、知らず知らずのうちに低栄養状態になってしまうリスクが高い
● 入院中の高齢者の半数が低栄養状態にある
● 在宅療養の高齢者の約7割が栄養の問題を抱えている
低栄養状態が続くと、筋肉量の減少や転倒リスクの増加・嚥下力の低下や誤嚥リスクの増加・免疫力の低下が引き起こされ、その結果、在宅高齢者の緊急入院や入院による心身の衰弱につながるという悪循環が生まれます。
人生100年時代の今こそ、感動を得られる食体験、元気に生きるための食支援が重要であると芳村氏は強調しました。

「あなたのマドレーヌは何ですか?」──記憶と感情を呼び起こす食の力
続いて、ヨーロッパの郷土料理や菓子、食文化の研究・紹介を行う株式会社オフィス・フェーヴの並木麻輝子(なみき まここ)氏が「食の旅」と称して、食が持つ記憶と感情のつながりについて語りました。
フランスの作家プルーストの小説『失われた時を求めて』では、主人公がマドレーヌを一口食べた瞬間、幼少期の記憶がよみがえるという象徴的なシーンがあります。この話を受けて並木氏は、フランスには「あなたのマドレーヌは何ですか?」(=あなたにとって大切な思い出は何ですか?)という言葉があることを紹介しました。
「食」は単なる栄養源ではなく、人生の記憶や感情と深く結びついているのです。
今回、会場では山梨県富士川町の香り高い柚子を使った「柚子マドレーヌ」が提供されました。並木氏は、食材の背景にあるストーリーを知ることが、食の楽しみをより豊かにすると述べました。
さらに、この柚子マドレーヌには「エネクイック」という高エネルギー粉末油脂が加えられ、高齢者でも楽しめる、おいしく栄養価の高いスイーツとして提供されました。
並木氏の話を受け、山梨県で農産物の開発・生産・加工・販売を行い、レーズンサンド専門店「葡萄屋kofu」を営む株式会社プロヴィンチアの古屋浩(ふるや ひろし?)氏は、自身を含めたシニア世代の食に対する意識について「歳をとっても、自分の納得できるものを食べたい」と語りました。
特に中小企業や個人のケーキ屋が、専門家の指導を受けながらシニア向けのスイーツを開発することで「食べる楽しみ」と「健康」の両立が可能になると期待を示しました。
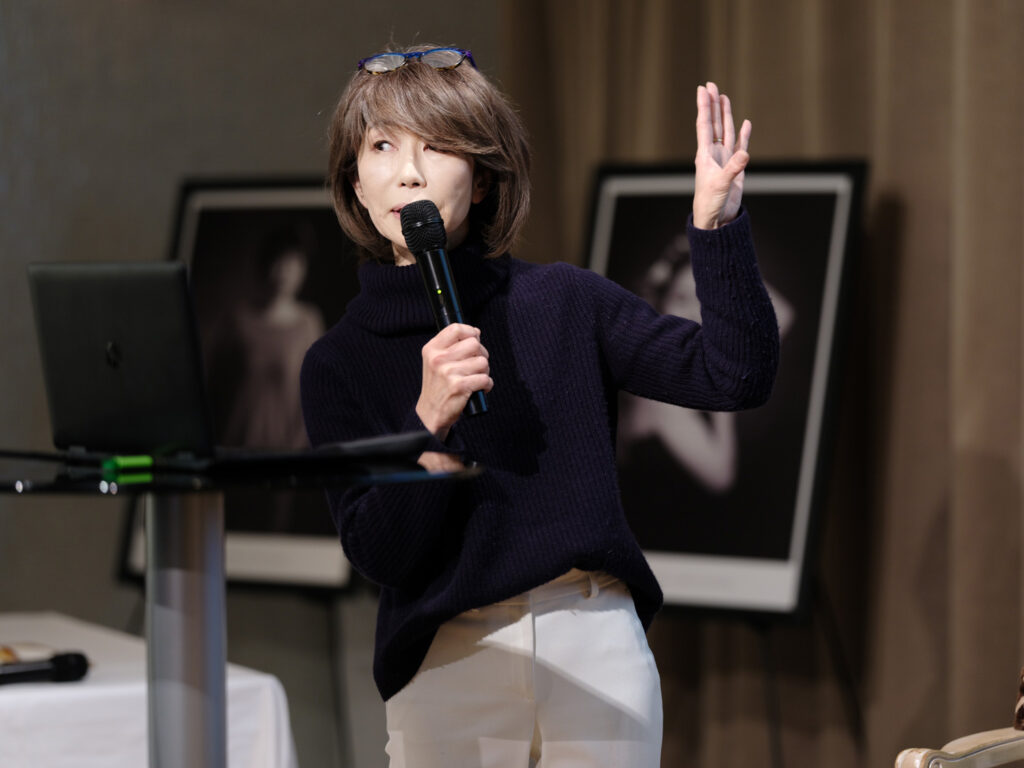
シルバーエコノミーを拡張する「食の多様性」と「楽しみ方」
セッションの最後に、司会の小口氏が会場に「あなたのマドレーヌは何でしょうか?」と問いかけ、「『私のマドレーヌ』が何歳になっても食べられる社会が自分らしい社会なのではないでしょうか」と続けました。
「歳をとったから『固いものはやめましょう』『熱いものは危ないからやめましょう』ではなく、どうやったら私のマドレーヌを楽しめるのかとみんな一緒になって考えていくこと」の重要性、自分らしさを支える食において、アイディアを発揮できる機会がある介護・福祉業界の可能性について語り、締め括りました。
このセッションでは、シルバーエコノミーの発展に繋がり得る、次の3つの大きな示唆が与えられました。
● 健康を維持しながら、人生を楽しめる食の選択肢を提供することが、今後の市場価値を生み出す
● 企業と専門家が連携し、シニア向けの「おいしくて楽しい食」を開発することで、新たなビジネスチャンスが生まれる
● 「『あなたのマドレーヌ』を何歳になっても楽しめる社会」を実現することが、シルバーエコノミーの本質
シルバーエコノミーの可能性は、介護や医療の領域だけに留まりません。「食」という身近なテーマを通じて、シニア世代がより豊かに、自分らしく生きる社会を創ることが、これからの重要な課題となるでしょう。

他セッション
「International KAiGO Festival 」とは
高齢化を脅威ではなく成長のチャンスと捉え、介護とシルバーエコノミーを変革
——KAiGOが日本と世界の未来を動かす答えと機会を生み出す場
3人に1人が65歳以上という急速な高齢化に直面している日本。介護職不足や約9兆円の経済損失などの課題を抱える一方、シルバーエコノミーは100兆円規模に成長する見込みです。「International KAiGO Festival」は、日本が世界に誇る介護の知見をさらに進化させ、介護を中心とした経済・社会のエコシステムを共創するプラットフォームとして立ち上げられました。スタートアップ、企業、政策立案者、投資家、介護職が集い、セッションやアワードを通じて次世代のビジネスモデルや技術革新を促進。「介護エコシステム」創出につながる業界を超えた価値ある学びが得られるインキュベーションの場として、日本と企業の未来を支援します。

「KAiGO PRiDE」とは
KAiGO PRiDEは、誰もが自分らしく安心して暮らせる社会の実現のため、クリエイティブの力で日本の介護を拡張・強化するプロジェクト。人類史に類をみない超高齢社会の日本では2040年に57万人の介護職が不足すると言われるなかで、私たちがライフクリエイターと呼ぶ全国の介護職・福祉職たちのSelf-respectを醸成し、社会からのリスペクトにつなげる「KAiGO-Branding」を展開。また、介護≠ケアとも言われ、私たちが世界一だと信じる日本の介護の持続可能性のため、様々なプレイヤーの巻き込みを図る「KAiGO-Ecosystem」の形成を推進しています。介護をKAiGOとして、その可能性と誇りをクリエイティブの力で形にするプラットフォームとして多様なプロジェクトをグローバルに展開しています。