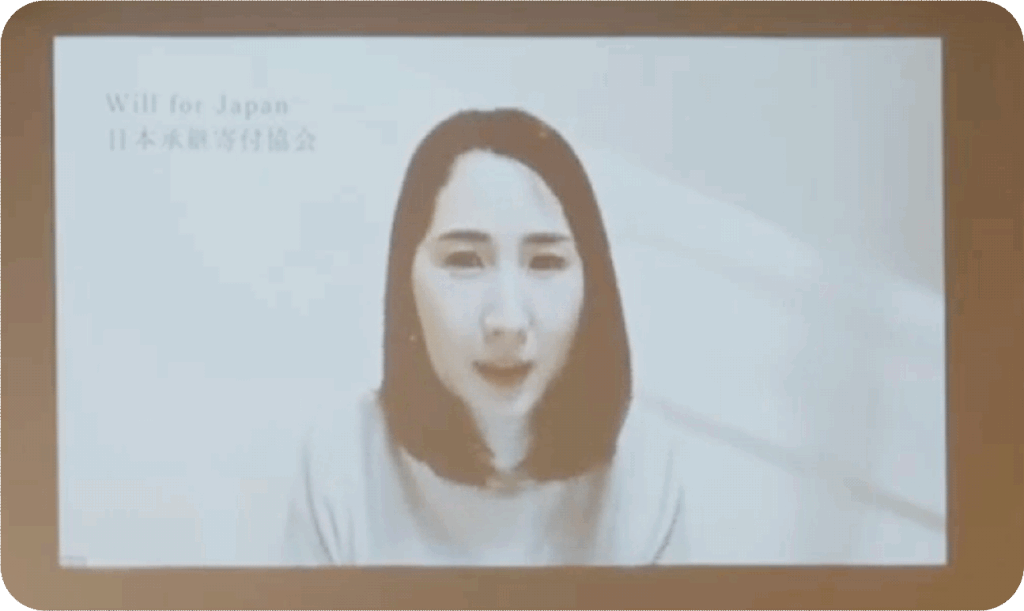Talk-Session vol.8「地域と世界をつなぐデザイン」
「自分らしく生きる」ためのデザイン
──シルバーエコノミーの可能性
登壇者プロフィール

羽田未来総合研究所 代表取締役社長執行役員
大西洋 様
1979年慶應義塾大学卒業、同年 伊勢丹入社。三越 常務執行役員MD統括部長、伊勢丹 常務執行役員等を経て、2012年三越伊勢丹ホールディングス代表取締役社長執行役員、三越伊勢丹 代表取締役社長執行役員に就任。2018年6月より日本空港ビルデング 取締役副社長、同年7月より羽田未来総合研究所 代表取締役社長を兼任。羽田空港内外で新しい価値創造を目指し、地方創生、文化・アートの発信に力を入れている。

kumicom代表
松下久美 様
ゴルフウェアの販売・バイイングを経て、「日本繊維新聞」流通記者として百貨店・専門店・量販店・商業施設などを担当。2003年にINFASパブリケーションズ(現)に入社し、「WWDジャパン」で国内外の小売り・アパレル・ラグジュアリー企業などを担当。デスク、シニアエディターを歴任。17年に独立し、取材・執筆や講演、アドバイザーなどを手掛けている。

一般社団法人KAiGO PRiDE 代表理事
マンジョット・ベディ
「just on time」代表/「next is east」代表/エグゼクティブクリエイティブディレクター/カメラマン。1969年インド・ニューデリー生まれ。外交官の父の仕事で、2歳より世界各地を巡り、17歳で来日。1997年広告会社に入社。クリエイティブ・ディレクターとして伊勢神宮、トヨタ自動車/レクサス等数々のCMを制作。2015年からは、熊本の常設型認知症カフェ「as a cafe」の企画・運営をプロデュース。
セッションの様子
高齢化社会は、日本経済にとって課題であると同時に大きなビジネスチャンスです。本トークセッションでは、シルバーエコノミーが生み出す新たな市場と、デザインの力が果たす役割について、取材・執筆、企業アドバイザーなどを通じて、企業や人をつなげ、ソーシャルグッドな未来を創るサポートを行うkumicom代表の松下久美(まつした くみ)氏をファシリテーターに、羽田未来総合研究所の大西洋(おおにし ひろし)氏と一般社団法人KAiGO PRiDEの代表理事のマンジョット・ベディの間で議論が交わされました。
シルバーエコノミーの可能性──課題ではなく市場機会として捉える
セッションは、大西氏の紹介から始まりました。大西氏は、地方創生・アート・人材・マーケティングなどの領域で活動しており、特に、地方創生においては「地方にある良いものを海外に発信したい」と日本の持つ価値を世界に発信することの重要性を語りました。
続いて、長年広告業界に携わってきたマンジョット・ベディが、日本における高齢化の現状とその可能性について言及しました。
「皆さん、必ず年を取っていくんですよ。年取らない人は誰1人いないんです」と会場に語りかけたマンジョットは、自身が海外で見てきた高齢者向けのサービスや商品について触れ、「ヨーロッパでは、眼鏡や靴、杖、車椅子までもがおしゃれにデザインされている」と述べました。
しかし、日本では「おしゃれな高齢者向け商品はあるが、非常に高価で手が届きにくい」と指摘し、「自分らしく生きる」ための選択肢を増やすことがビジネスチャンスにつながるとの見解を示しました。
さらに、マンジョットは、「日本は確かに高齢者が増える。だからといって、暗いことばかりではない」と述べ、高齢化を新たな技術の向上とビジネス機会として捉えることが重要であると強調しました。これは、シルバーエコノミーの本質的な考え方といえるでしょう。

リバースエイジングと新しい価値創造──シルバー世代が生き生きと活躍できる社会へ
セッションの中で「リバースエイジング(加齢に逆らう)」の概念についても議論が展開されました。
大西氏は、「フィジカルなリバースエイジングはすでに実現しつつあるが、重要なのは世代間の交流や価値観の共有である」と指摘。「いくつになっても希望を持てる社会をどう作るかが、シルバーエコノミーの成功の鍵になる」であることを示唆しました。
また、日本財団の調査結果を引用し、日本の若者の社会への意識についても言及。18歳の若者たちのうち「自分で国や社会を変えられると思うか」という問いに対し、「そう思う」と回答したのは、たった18%。50%から60%の諸外国と比較しても、非常に低い結果です。
マンジョットはこのデータを踏まえ「KAiGO Festivalをやりたい理由の出発点」と語りました。若い世代が社会に対して希望を持てるような環境を作ることの大切さ。そのために、シニア世代の生き方を見直し、彼らが活躍できる社会をデザインすることが必要性が語られました。
また、松下氏から「クリエイティブなものづくりが若者と高齢者をつなぐ可能性」についての問いが投げかけられました。これに対し、大西氏は「日本の強みはクリエイティビティにある」と述べ、傘の部品やネジ、半導体など、世界的に高く評価されている日本のものづくり文化を例に挙げました。
マンジョットもこれに賛同し、「日本はクリエイティブでは強いが、マーケティングが苦手」だと指摘。「良いものを作っても、それが世界に伝わっていない」とし、デザインとマーケティングを融合させることが、日本のシルバーエコノミー市場拡大の鍵になると述べました。

アントレプレナーシップと市場規模100兆円の未来
シルバーエコノミーの市場規模は、2030年には100兆円に達すると予測されています。この巨大市場に対し、起業家や企業がどのように参入できるのかも議論の中心となりました。
松下氏が「起業を考えている人にとって、どのようなチャンスがあるのか?」と問いかけると、マンジョットは「KAiGO Festivalのような場を通じて、挑戦したい人を支援していきたい」と述べました。
さらに、「我々はユニコーン(急成長するスタートアップ)ではなく、ゼブラ(社会貢献とビジネスを両立する企業)を目指していきたい」と語り、利益だけでなく、次世代や社会、地球のことを考えながら事業を展開することの重要性を強調。
また、大西氏は、日本の起業率が欧米に比べて低い現状に触れつつ、近年は社会課題の解決を目的とした起業が増えていると指摘。介護やシルバーエコノミーをテーマにした起業はまだ市場のポテンシャルに追いついていないともメッセージしました。
特に、高齢者の「自分の感性を維持して豊かに生きたい」という願いに対して、流通小売業・飲食業が応えられていない現状があります。大西氏は、そこに大きなマーケット、ブルーオーシャンが広がっていることを強調しました。

シルバーエコノミーの先駆者となるには?
本セッションを通じて、シルバーエコノミーが単なる高齢者向け市場ではなく、若者とシニアが共に価値を創造する新しい経済圏であることが示されました。
● 高齢化は課題ではなく、新たな市場機会である
● デザインの力を活用し、高齢者が「自分らしく生きる」社会を実現する
● アントレプレナーが積極的に参入し、シルバー市場を活性化させることが重要
今後、シルバーエコノミーを推進するためには、企業と行政の連携、デザインとテクノロジーの活用、そして何よりも「高齢化をポジティブに捉える社会のマインドセット」が不可欠です。
高齢化が進む日本において、新たなビジネスと価値を創出し、世界へと発信していく。シルバーエコノミーの未来は、まさにこれから拓かれていきます。
他セッション
「International KAiGO Festival 」とは
高齢化を脅威ではなく成長のチャンスと捉え、介護とシルバーエコノミーを変革
——KAiGOが日本と世界の未来を動かす答えと機会を生み出す場
3人に1人が65歳以上という急速な高齢化に直面している日本。介護職不足や約9兆円の経済損失などの課題を抱える一方、シルバーエコノミーは100兆円規模に成長する見込みです。「International KAiGO Festival」は、日本が世界に誇る介護の知見をさらに進化させ、介護を中心とした経済・社会のエコシステムを共創するプラットフォームとして立ち上げられました。スタートアップ、企業、政策立案者、投資家、介護職が集い、セッションやアワードを通じて次世代のビジネスモデルや技術革新を促進。「介護エコシステム」創出につながる業界を超えた価値ある学びが得られるインキュベーションの場として、日本と企業の未来を支援します。

「KAiGO PRiDE」とは
KAiGO PRiDEは、誰もが自分らしく安心して暮らせる社会の実現のため、クリエイティブの力で日本の介護を拡張・強化するプロジェクト。人類史に類をみない超高齢社会の日本では2040年に57万人の介護職が不足すると言われるなかで、私たちがライフクリエイターと呼ぶ全国の介護職・福祉職たちのSelf-respectを醸成し、社会からのリスペクトにつなげる「KAiGO-Branding」を展開。また、介護≠ケアとも言われ、私たちが世界一だと信じる日本の介護の持続可能性のため、様々なプレイヤーの巻き込みを図る「KAiGO-Ecosystem」の形成を推進しています。介護をKAiGOとして、その可能性と誇りをクリエイティブの力で形にするプラットフォームとして多様なプロジェクトをグローバルに展開しています。