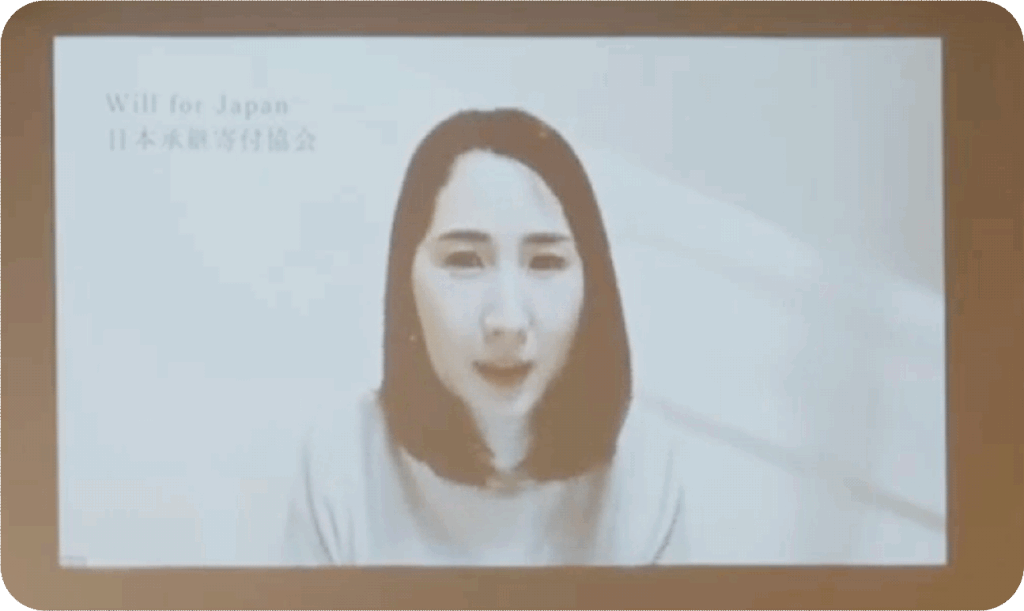Talk-Session vol.7「KAiGO STARTUP STORIES part1」
介護業界の変革への挑戦
──マインドシフト・DXによる価値創造
登壇者プロフィール

株式会社最中屋 CEO
結城崇 様
電機メーカの半導体部⾨で商品企画、営業に従事。同インド部⾨の新規事業開発にて、介護という社会課題解決が⾃⾝の使命であることを悟り、同介護部⾨で、責任者を歴任。AIベンチャーへ参画。ケアイノベーションコンサル、AIアプリプロダクトオーナー、介護ドメインスペシャリストとして、介護ソフトメーカへ出向の後独⽴。団体理事や委員を努めながら、エバンジェリスト=伝道者として介護ICTの普及促進・介護DX推進に邁進する。

一般社団法人KAiGO PRiDE 理事
石本淳也
(一社)熊本県介護福祉士会会長/(公社)日本介護福祉士会前会長。熊本県八代市出身。1971年生まれ。1992年から熊本市の特別養護老人ホームで介護職として働きだす。その後、2004年から介護老人保健施設に転職。2008年度より(一社)熊本県介護福祉士会会長に就任し(現職)、2016年度より(公社)日本介護福祉士会会長に史上最年少で就任、2020年6月末に退任。現在は熊本市内の特別養護老人ホームの施設長を務める。
セッションの様子
介護職の人材不足とその背景にある「業界のイメージ」問題
高齢化が進む日本において、介護業界は社会の持続性を左右する重要な分野です。しかし、介護職の人材不足や業界のイメージの問題など、多くの課題が横たわっています。今回は、株式会社最中屋 CEOの結城崇(ゆうき たかし)氏、一般社団法人KAiGO PRiDE 理事の石本淳也により、介護を機会に変えた企業の実践と、社会を変えるそのビジョンが語られました。
トークセッションの冒頭、石本は「介護福祉士の資格保持者約190万人のうち、実際に介護の現場で働いているのは半数に過ぎない」という現状を共有しました。国としても介護人材の確保に取り組んでいますが、なかなか成果が上がっていないのが実情です。
特に、今後15年で85歳以上の人口が1000万人を突破することが確実視されている中で、介護職の確保は「業界を越えた国民的課題」であると強調しました。
また、介護業界には「8K(きつい・汚い・危険・臭い・休日が取れない・給料が安い・結婚できない・子どもが産めない)」や「9K(さらに『腰が痛い』が加わる)」といった、ネガティブなイメージが根強く残っていると指摘しました。このようなイメージは、外部からではなく、業界内部の当事者たちによって語られ続けた結果、広まってしまったと分析しています。
しかし、石本自身の経験として、介護職に従事しながら結婚し、子育てもでき、休日も取得できる環境が整ったことを例に挙げ、実際の現場はイメージとは異なることをメッセージしました。
石本が理事を務めるKAiGO PRiDEは、介護職の誇りを取り戻し、社会全体からのリスペクトを生み出すための活動を行っています。その核となるのが、介護職自らが仕事の価値を発信し、ネガティブなイメージをポジティブに転換することです。「セルフリスペクト」という考え方を掲げ、自分たちの仕事をまず自ら尊敬し、その誇りを社会に伝えていくことの重要性を訴えました。
さらに石本は、制度的なアプローチや生産性向上の必要性にも触れながら、「僕が大切だと思うのは、当事者がマインドチェンジをして、仕事にしっかりと誇りを持つ、誇りを持てるように学ぶ、専門性を担保し、国民の皆様に安心してケアが受けられる社会を提供する、それを保障していく。それをケアワーカーみんながシェアしていくということ」と語りました。
介護の課題を「機会」に変えるビジネスモデルとは?
続いて登壇した結城氏は、石本の「8K」に対し、結城氏は「介護は3K(感謝・感動・感激)だ」と述べました。実際に、黒字経営を維持しながら充実した福利厚生を実現している介護事業者の例を挙げ、「介護は適切な経営をすれば持続可能なビジネスになり得る」と示唆しました。
その具体例として、経済産業省と連携した介護ロボット分野の見直しや、保険外サービスの展開について言及しました。特に、認知機能の低下状態をデジタルで可視化し、適切なケアにつなげる取り組みを進めていることを紹介。
さらに、会社のビジョン「まん中でケアする人をおもてなし。」とあわせて、プロダクトのコンセプトについて、「人間的な介護のための科学的アプローチ」を実践し、OODAループを活用した生産性向上を目指していると説明。介護現場では、まず「観察」から始まり、「仮説を立てる」「共同で意思決定を行う」「行動する」というプロセスを繰り返すことで、より良いケアが実現されると述べました。
「このループを現場で回していくことを、我々のプロダクトがサポートしていく」とし、テクノロジーを活用しながらも、最終的には「人間的な介護」の質を高めることが重要だと強調しました。
また、介護業界の課題として、以下の2点を指摘しました。
1.介護の現場では、入院すると要介護度が上がる傾向がある
● 入院の理由の大半は、肺炎・骨折・心不全・脱水など、予防可能なものが多い
● しかし、介護施設にいてもこれらの事態が発生してしまっている
2.介護現場では「直接的なケア」に十分な時間が割けていない
● 介護スタッフが間接業務に多くの時間を取られてしまい、利用者のケアに集中できない
この問題を解決するため、結城氏が率いる最中屋は、デジタル技術を活用した新たなビジネスモデルを展開しています。
例えば、「ハカルト」というシステムを用いた業務分析により、介護スタッフがどの業務にどれくらい時間を使っているかを可視化し、改善策を提案しています。これにより、直接的なケアの時間を増やし、介護の質を向上させることが可能になります。
「生産性向上とは『人を減らすこと』ではなく、『直接ケアの時間を増やすこと』」
結城氏はこのように述べ、介護業界における生産性向上の本質について語りました。

シルバーエコノミーがもたらす社会の進化
今回のトークセッションでは、介護業界の課題を乗り越え、シルバーエコノミーを加速させるための重要な視点が共有されました。
● 介護職の価値を正しく伝え、ポジティブなイメージを広めることが人材確保につながる
● 適切な経営と生産性向上によって、介護業界は持続可能なビジネスになり得る
● デジタル技術の活用により、介護と医療の垣根をなくし、より良いケアを実現できる
超高齢社会の到来に伴い、介護を「負担」ではなく「機会」と捉える視点がますます重要になります。介護業界の変革こそが、シルバーエコノミーの未来を拓く鍵となるでしょう。

他セッション
「International KAiGO Festival 」とは
高齢化を脅威ではなく成長のチャンスと捉え、介護とシルバーエコノミーを変革
——KAiGOが日本と世界の未来を動かす答えと機会を生み出す場
3人に1人が65歳以上という急速な高齢化に直面している日本。介護職不足や約9兆円の経済損失などの課題を抱える一方、シルバーエコノミーは100兆円規模に成長する見込みです。「International KAiGO Festival」は、日本が世界に誇る介護の知見をさらに進化させ、介護を中心とした経済・社会のエコシステムを共創するプラットフォームとして立ち上げられました。スタートアップ、企業、政策立案者、投資家、介護職が集い、セッションやアワードを通じて次世代のビジネスモデルや技術革新を促進。「介護エコシステム」創出につながる業界を超えた価値ある学びが得られるインキュベーションの場として、日本と企業の未来を支援します。

「KAiGO PRiDE」とは
KAiGO PRiDEは、誰もが自分らしく安心して暮らせる社会の実現のため、クリエイティブの力で日本の介護を拡張・強化するプロジェクト。人類史に類をみない超高齢社会の日本では2040年に57万人の介護職が不足すると言われるなかで、私たちがライフクリエイターと呼ぶ全国の介護職・福祉職たちのSelf-respectを醸成し、社会からのリスペクトにつなげる「KAiGO-Branding」を展開。また、介護≠ケアとも言われ、私たちが世界一だと信じる日本の介護の持続可能性のため、様々なプレイヤーの巻き込みを図る「KAiGO-Ecosystem」の形成を推進しています。介護をKAiGOとして、その可能性と誇りをクリエイティブの力で形にするプラットフォームとして多様なプロジェクトをグローバルに展開しています。