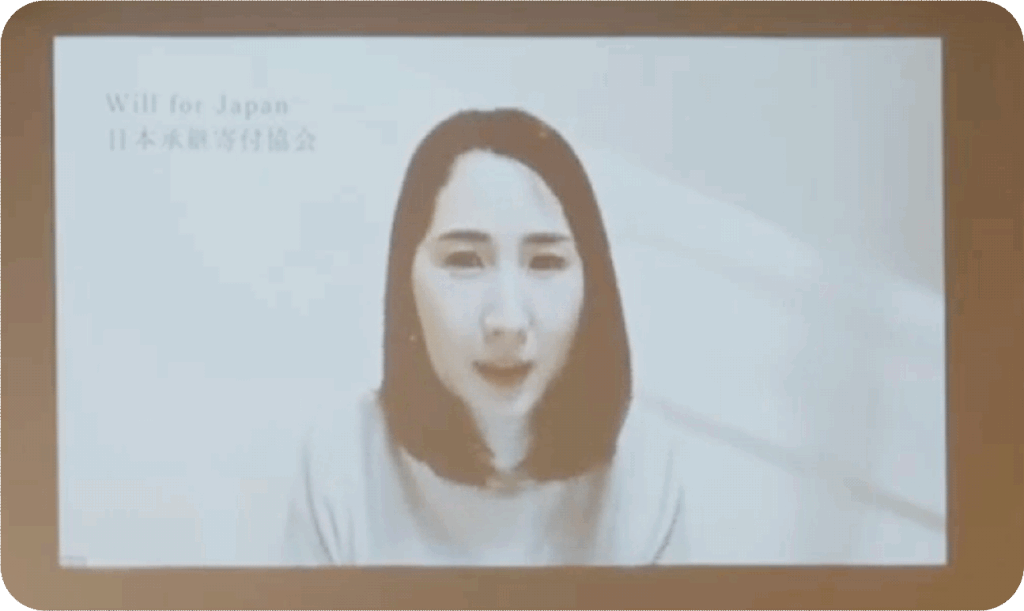Talk-Session vol.1「高齢化の進化」
高齢化の進化がもたらすビジネスチャンス
──シルバーエコノミーの未来を拓く官民の挑戦
登壇者プロフィール

株式会社ルネサンス 執行役員
樋口毅 様
1997年 順天堂大学大学院 修士課程を修了後、複数の企業で、健康管理・労働政策・保健事業・健康サービス開発など、「働く人の健康」に関わる業務に携わる。2013年に、健康価値共創を目的に「健康経営会議」を立ち上げ、健康経営を通じたヘルスケア産業の社会実装に取り組む。

経済産業省商務・サービスグループヘルスケア産業課
水口怜斉 様
経済産業省商務・サービスグループヘルスケア産業課にて、介護政策振興、医療ヘルスケアの国際展開支援、ヘルスケアスタートアップ振興等の政策立案を担当。その他、入省後、スタートアップ支援や起業家育成、大阪・関西万博関連業務、大学ファンドの立ち上げにも従事。

経済産業省商務・サービスグループヘルスケア産業課
沼澤駿斗 様
経済産業省商務・サービスグループヘルスケア産業課にて、ヘルスケア分野の政策立案を担当。認知症施策を中心に、共生社会の実現に資するイノベーションの創出とその仕組みづくりを推進。
セッションの様子
「生涯現役」社会の実現に向けた課題と展望
「皆さんは何歳まで働かれますか?」——この問いから始まった本トークセッション。会場で最も多かった回答は「70歳まで」。少子高齢化が進む日本において、理想とされる「生涯現役」という回答は最も少ない結果に。まるで、現在の社会課題を象徴しているようです。
今回は、その課題を乗り越えるべく、生涯現役社会と当事者参画を目指す政府の取り組み、その結果見出された新たなビジネスチャンスが語られました。「『高齢化の進化』に必要なこととは何か」官民それぞれの視点で熱く議論が交わされました。
ファシリテーターの株式会社ルネサンスの樋口毅(ひぐち つよし)氏は、企業の健康経営において「介護」を取り扱う企業が限定的であることを指摘。また、日本で最も多い労働災害が「転倒」であり、その中でも「何もないところで転倒する」ケースが最も高い割合を占めること、特に小売業・社会福祉施設・飲食店で労働災害が多いことを説明。「高齢者が活躍できる企業づくり」が今後の重要課題であると語りました。
前提となる現在の課題を整理した上で、樋口氏は参加者に「『高齢化の進化』に何が必要なのか」を考えながらセッションに臨むよう呼びかけました。

シルバーエコノミーを加速させる官民の取り組み
経済産業省の水口怜斉(みずぐち りょうせい)氏は、「高齢化・高齢者という言葉をなくしていきたい」という想いを語り、「これからの介護とビジネス」と題して政府の取り組みを紹介しました。
仕事と介護の両立困難により労働の生産性等が下がっていること。その結果、日本全体の経済損失は2030年には約9.2兆円に上ること。データに基づいて、これらの課題を指摘した上で、家族介護者の負担を減らすための新たなビジネスモデルや経産省が推進している施策について語りました。例えば、愛知県豊明市では、民間事業者と協業し、公的保険外サービスを開発。これにより、小売店の顧客単価を向上させることに成功しました。他にも、介護を「個人の課題」から「みんなの話題」へ転換することを目指す「OPEN CARE PROJECT」などの取組について紹介がありました。
さらに、同じく経済産業省の沼澤駿斗(ぬまざわ はやと)氏から、認知症の方が企業の開発プロセスに参画し、新たな価値を生み出すことを目的とした「オレンジイノベーション・プロジェクト」の推進について語られました。この取り組みでは、認知症当事者の視点を取り入れた商品開発が進められているとのこと。
認知症当事者に限らず、すべての人にとって使いやすいユニバーサルデザインを実現している具体的な成果として、
● リンナイ株式会社「誰でも安心して使えるガスコンロ『SAFULL+(セイフルプラス)』」
● 株式会社大醐「誰でも履きやすい靴下『Unicks(ユニークス) カカトがない靴下』」
● YKK株式会社「誰でも開け閉めがしやすいファスナー『click-TRAK® Magnetic』」(オレンジイノベーション・アワード2024 最優秀賞受賞)
といった製品が生まれていることが紹介されました。

「高齢化の進化」が生み出す新たな市場機会
トークセッションの終盤に樋口氏によって投げかけられた「『高齢化の進化』に何が必要か?」という問いに、水口氏は「ロールモデルの存在」、沼澤氏は「新しい認知症観」が重要だと回答しました。
水口氏は「介護の現場ではシニアがシニアを支えるケースが増えている」と指摘し、シニア自身が前向きに活躍できるロールモデルの必要性を語りました。会場でも「豊かな高齢期の過ごし方を学んだことがある人」「認知症になったときの豊かな生き方を学んだことがある人」と質問したところ、手を挙げられる方はなく、日本社会における「ロールモデルの不在」を象徴する光景でした。
また、沼澤氏は「エイジズム(加齢による差別)が認知症の人にも起きている」と指摘し、「認知症の人に対する偏見をなくすことが、ビジネスにおいても社会全体にとっても重要である」と述べました。
樋口氏は、水口氏と沼澤氏から共有された政策は「課題をどう価値に転換できるか」が共通のキーワードだったと述べ、次のように問題提起しました。
「例えば、認知症の当事者との共生社会というのは(中略)認知症1000万人いる人たちに対して、どういう市場が形成できるのかという価値創造の視点だと思います。若い人たちを介護に取り込んでいこうというのも、新しい価値を生み出すために、今の若者世代が新しい価値を見出していくためのチャレンジの場を作るということ」
「高齢化を進化させていくというのは(中略)課題解決の視点から価値創造の視点を作るということ」

シルバーエコノミーがもたらす未来とは?
このトークセッションでは「高齢化は課題ではなく新たな市場機会である」という視点が繰り返し語られ、それは次のとおり3つにまとめられます。
● 労働力不足を解決し、生涯現役社会を実現することが、企業にとっても利益につながる
● 介護や認知症の問題を新たなビジネスチャンスとして捉え、企業と行政が連携することが重要
● シニア世代のロールモデルを確立し、社会全体の価値観をアップデートすることが求められる
要支援・要介護者700万人、認知症・軽度認知障害を持つ1000万人を市場・資本と捉え、新たな価値創造に繋げることが、無限に広がるシルバーエコノミーの可能性を活かす鍵といえるでしょう。
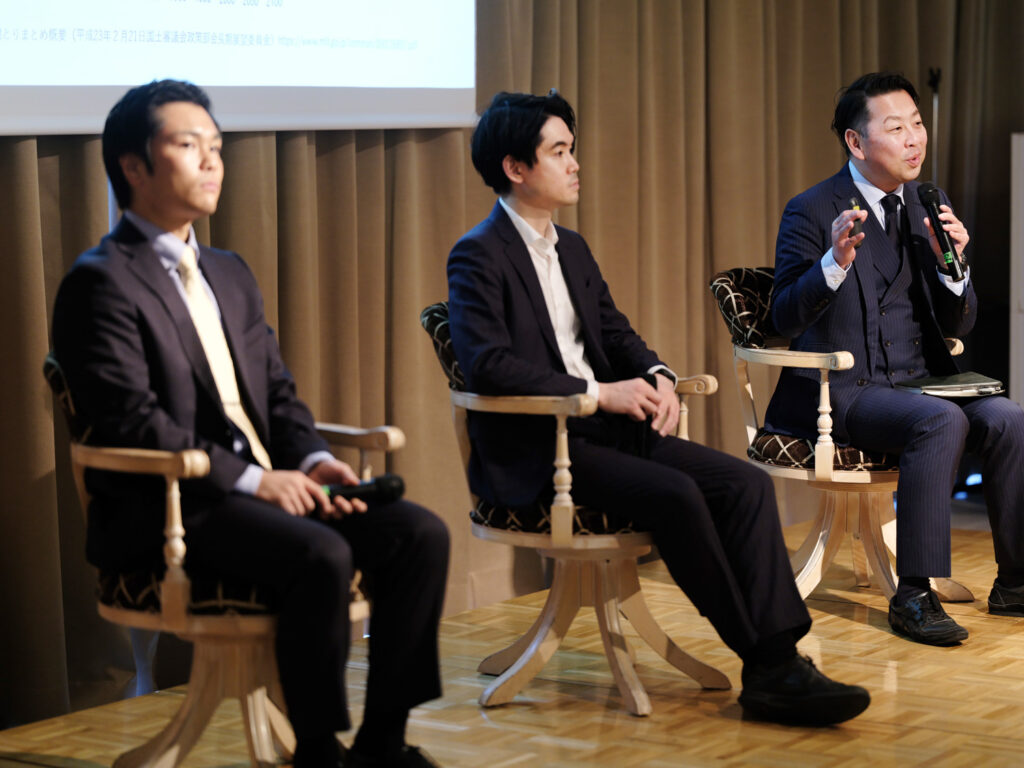
他セッション
「International KAiGO Festival 」とは
高齢化を脅威ではなく成長のチャンスと捉え、介護とシルバーエコノミーを変革
——KAiGOが日本と世界の未来を動かす答えと機会を生み出す場
3人に1人が65歳以上という急速な高齢化に直面している日本。介護職不足や約9兆円の経済損失などの課題を抱える一方、シルバーエコノミーは100兆円規模に成長する見込みです。「International KAiGO Festival」は、日本が世界に誇る介護の知見をさらに進化させ、介護を中心とした経済・社会のエコシステムを共創するプラットフォームとして立ち上げられました。スタートアップ、企業、政策立案者、投資家、介護職が集い、セッションやアワードを通じて次世代のビジネスモデルや技術革新を促進。「介護エコシステム」創出につながる業界を超えた価値ある学びが得られるインキュベーションの場として、日本と企業の未来を支援します。

「KAiGO PRiDE」とは
KAiGO PRiDEは、誰もが自分らしく安心して暮らせる社会の実現のため、クリエイティブの力で日本の介護を拡張・強化するプロジェクト。人類史に類をみない超高齢社会の日本では2040年に57万人の介護職が不足すると言われるなかで、私たちがライフクリエイターと呼ぶ全国の介護職・福祉職たちのSelf-respectを醸成し、社会からのリスペクトにつなげる「KAiGO-Branding」を展開。また、介護≠ケアとも言われ、私たちが世界一だと信じる日本の介護の持続可能性のため、様々なプレイヤーの巻き込みを図る「KAiGO-Ecosystem」の形成を推進しています。介護をKAiGOとして、その可能性と誇りをクリエイティブの力で形にするプラットフォームとして多様なプロジェクトをグローバルに展開しています。