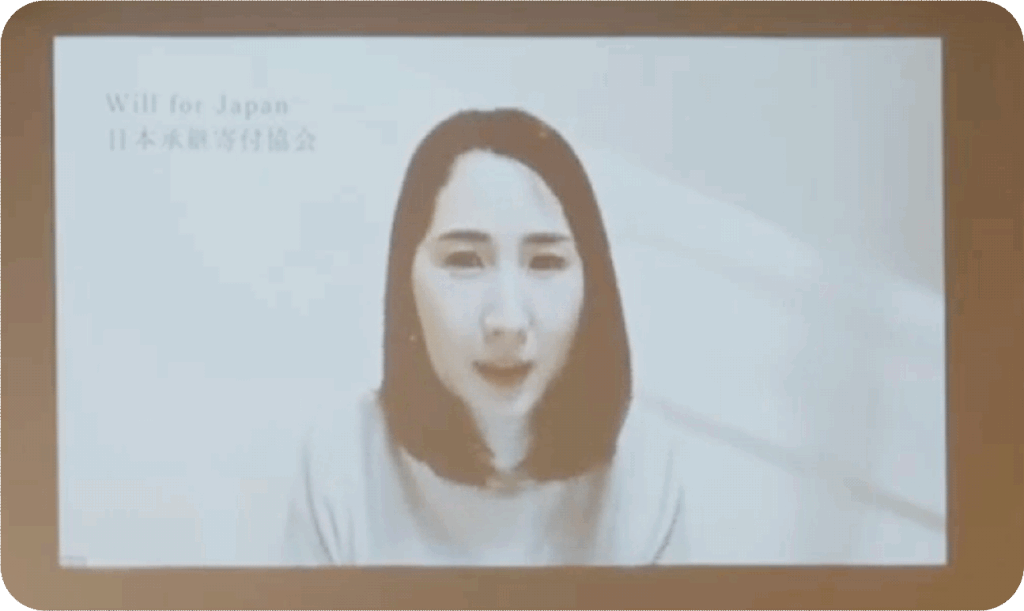Talk-Session vol.9「KAiGO STARTUP STORIES part2」
高齢化を機会に変える
──企業の実践と未来へのビジョン
登壇者プロフィール

株式会社Yume Cloud Japan 代表取締役
吉田大輔 様
1997年 順天堂大学大学院 修士課程を修了後、複数の企業で、健康管理・労働政策・保健事業・健康サービス開発など、「働く人の健康」に関わる業務に携わる。2013年に、健康価値共創を目的に「健康経営会議」を立ち上げ、健康経営を通じたヘルスケア産業の社会実装に取り組む。

ユカイ工学株式会社 COO
鈴木裕一郎 様
経済産業省商務・サービスグループヘルスケア産業課にて、ヘルスケア分野の政策立案を担当。スタートアップ支援や起業家育成、大阪・関西万博関連業務、大学ファンドの立ち上げにも従事。医療・福祉・健康分野を横断したヘルスケア産業の振興に取り組む。
セッションの様子
健康経営が企業価値を高める時代へ
今回のセッションでは、シルバーエコノミーの可能性を探るべく、高齢化をビジネスチャンスに変えた企業の具体的な取り組みと、それが社会にもたらす影響が語られました。
登壇者は、株式会社Yume Cloud Japanの代表取締役・吉田大輔(よしだ だいすけ)氏と、ユカイ工学株式会社のCOO・鈴木裕一郎(すずき ゆういちろう?)氏。健康経営の重要性や、ロボティクスを活用した高齢者支援といった視点から、今後のビジョンが語られました。
最初に登壇した吉田氏は、「健康経営」の概念について解説しました。
「欧米のビジネスパーソンは自主的に心身の状態を管理するのが当たり前だが、日本ではその意識がまだ十分に根付いていない」ことを指摘し、従業員の健康を守ることが、企業の持続的な成長に直結することを強調しました。
日本企業に求められる「攻めの健康経営」
従来の健康経営は、社員の健康リスクを減らす「守り」の発想が主流でした。しかし、吉田氏は「これからの時代は、健康経営を攻めの視点で捉えることが重要」と述べ、次のようなポイントを挙げました。
● 健康経営に取り組む企業の株価は上がる
● 健康経営銘柄に認定されることが、人材獲得の要件になりつつある
● 健康をコストではなく投資と捉え、企業文化に組み込むことが必要
さらに、介護を抱える従業員への支援についても触れ、「個々人がセルフマネジメントできる環境を整えることが、企業にとっても重要な経営課題になっている」と述べました。
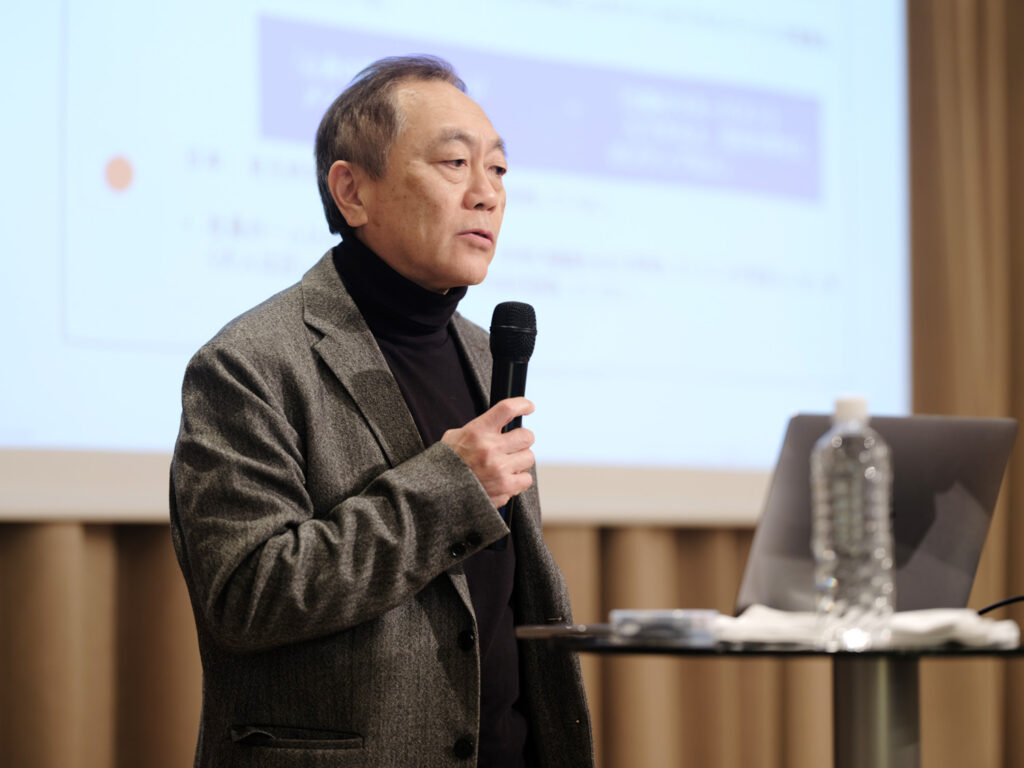
テクノロジーが変える高齢者の暮らしと介護支援
続いて、吉田氏はYume Cloud Japanの提供する「マインドスケールメソッド」を紹介しました。このメソッドは、生体データを30秒で測定し、ストレスやメンタルの状態を可視化する技術です。
「従業員のストレス状態を定期的に把握し、専門家が適切なアドバイスを提供することで、メンタル不調を未然に防ぐ」とし、今後の応用として「認知症やうつ病の一次診断への活用も期待されている」と語りました。
次に、ユカイ工学の鈴木氏が登壇し、「ロボティクスが高齢者の生活を豊かにする」ビジョンを語りました。
「心のつながり」を生むロボットの役割
ユカイ工学が開発する製品は、高齢者の見守りや心のケアに活用されています。代表的なものとして、以下の3つのプロダクトが紹介されました。
1.Qoobo(クーボ)
● しっぽを持つクッション型ロボット。撫でるとしっぽを振る動きが、心理的な癒しを提供。
● 累計5万台以上を販売し、シニア層にも人気。
2.甘噛みハムハム
● 赤ちゃんやペットの「甘噛み」感覚を再現するロボット。
● 累計6万台を販売。
3.BOCCO emo(ボッコ エモ)
● 家族のコミュニケーションをサポートするロボット。見守り機能やリマインダー機能を搭載。
● 一人暮らしの高齢者が「名前を呼んでもらう」ことで生活にメリハリが生まれたという声も。
鈴木氏はテクノロジーにより利便性だけでなく、心のつながりを生み出せると語りました。

官民連携×ロボットが拓く未来──高齢者支援の最前線
官民連携による新たな取り組み
鈴木氏は、企業と自治体が協力する具体例として、以下の取り組みを紹介しました。
● 広島県福山市では、買い物が困難な高齢者のために、ロボットが注文を受け、スーパーに発注するシステムを導入。
● 名古屋大学との研究では、自動車の運転中にロボットが音声で注意喚起することで、事故防止に貢献。
また、ハードウェアとしてのロボットの価値を名古屋大学の教授の言葉を借りて、「次元の一致」と表しました。同じ3次元にいることで、よりリアルに情報を受け取って信用するという人間の心理が働いているといいます。スマートフォンやスマートフォン越しのキャラクターにはない価値がロボットにはあります。
鈴木氏は「大切な人の近くにいたい、声をかけたいけどできない。物理的な制約や人間関係があるとき、そんなときロボットがそっと寄り添うミライをつくりたいと考えております」と締め括りました。

シルバーエコノミーの可能性──課題をチャンスに変える未来戦略
日本をはじめ、多くの国々が高齢化の進展という大きな社会変化に直面しています。しかし、これは単なる課題ではなく、新たな経済機会を生み出す可能性を秘めています。本日登壇した2社の取り組みから、次のような可能性が示唆されました。
● テクノロジーがもたらす課題解決と経済的インパクト
● 官民連携による持続可能なビジネスモデルの創出
テクノロジーと官民連携の力を最大限に活用することで、高齢化社会の課題を解決しながら、新たな経済成長を生み出す。シルバーエコノミーは、私たちにとっての「挑戦」であると同時に、「未来を創るチャンス」でもあるのです。

他セッション
「International KAiGO Festival 」とは
高齢化を脅威ではなく成長のチャンスと捉え、介護とシルバーエコノミーを変革
——KAiGOが日本と世界の未来を動かす答えと機会を生み出す場
3人に1人が65歳以上という急速な高齢化に直面している日本。介護職不足や約9兆円の経済損失などの課題を抱える一方、シルバーエコノミーは100兆円規模に成長する見込みです。「International KAiGO Festival」は、日本が世界に誇る介護の知見をさらに進化させ、介護を中心とした経済・社会のエコシステムを共創するプラットフォームとして立ち上げられました。スタートアップ、企業、政策立案者、投資家、介護職が集い、セッションやアワードを通じて次世代のビジネスモデルや技術革新を促進。「介護エコシステム」創出につながる業界を超えた価値ある学びが得られるインキュベーションの場として、日本と企業の未来を支援します。

「KAiGO PRiDE」とは
KAiGO PRiDEは、誰もが自分らしく安心して暮らせる社会の実現のため、クリエイティブの力で日本の介護を拡張・強化するプロジェクト。人類史に類をみない超高齢社会の日本では2040年に57万人の介護職が不足すると言われるなかで、私たちがライフクリエイターと呼ぶ全国の介護職・福祉職たちのSelf-respectを醸成し、社会からのリスペクトにつなげる「KAiGO-Branding」を展開。また、介護≠ケアとも言われ、私たちが世界一だと信じる日本の介護の持続可能性のため、様々なプレイヤーの巻き込みを図る「KAiGO-Ecosystem」の形成を推進しています。介護をKAiGOとして、その可能性と誇りをクリエイティブの力で形にするプラットフォームとして多様なプロジェクトをグローバルに展開しています。