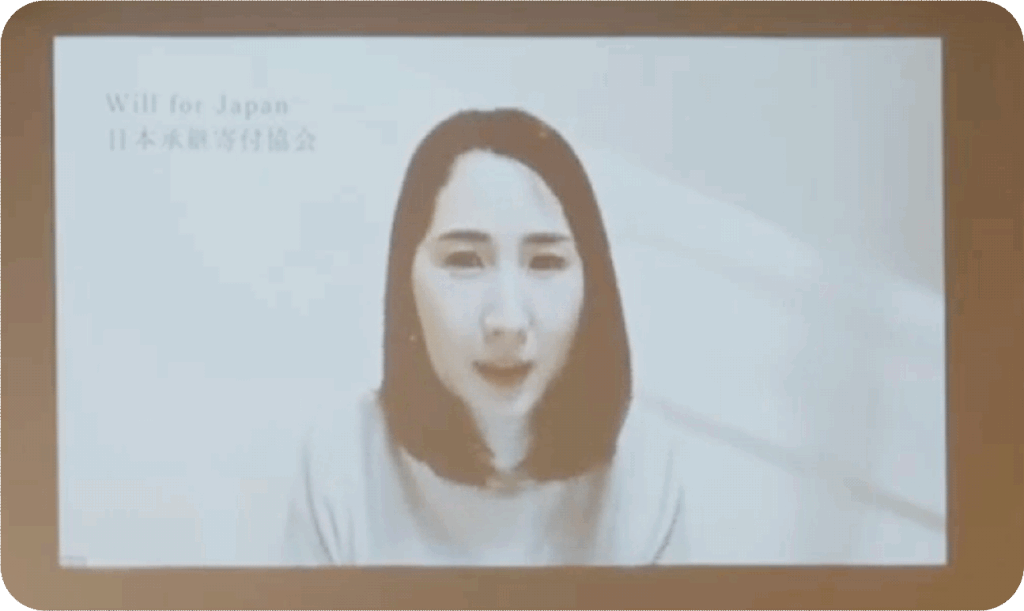Talk-Session vol.5「KAiGOの今」
KAiGOの最前線を知る
──介護の魅力発信が未来をつくる!
登壇者プロフィール

株式会社マガジンハウス こここ編集部
プロデューサー
及川 卓也 様
1988年からマガジンハウスにて編集者・メディアプロデューサーとして働く。anan編集長を経て、2012年 ローカルネットワークマガジン<コロカル>創刊。2021年 福祉をたずねるクリエイティブマガジン<こここ>創刊。2024年からは<こここ>ラボ・ディレクターとして福祉に関わるプロジェクトの活動を継続。人や地域の暮らし、生業、つながり、健やかなあり方などを考え、創造する場づくりのような活動を行う。

楽天グループ株式会社
林 様

朝日新聞社
小髙めぐみ 様
2005年朝日新聞社入社。名古屋本社を振り出しに、11年からは東京本社にて金融機関放送局、エンターテインメント産業等民間企業のメディアプロモーション業務を幅広くを経験。23年から官公庁・自治体の広報啓発事業を担当し、厚生労働省の介護の魅力発信等事業等に従事。その他には総務省、国土交通省、農林水産省や自治体、団体などの広報事業も経験。
セッションの様子
日本が直面する超高齢社会において、介護はもはや一部の人々だけの問題ではなく、社会全体で取り組むべき重要なテーマです。本トークセッションでは、KAiGO PRiDEとともに厚生労働省の「令和6年 介護のしごと魅力発信等事業」に採択された3つの事業者——マガジンハウス「こここ」編集部の及川卓也(おいかわ たくや)氏、楽天グループの林(はやし~)氏、朝日新聞社のオダカ氏が登壇。KAiGO PRiDEを通じて現役介護職とつながり、そのリアルを届けたそれぞれの視点から、介護の現状とその魅力を伝える取り組みが紹介されました。
メディア、デジタルマーケティング、教育の各分野でどのような施策が展開され、どんな成果が生まれているのか——その具体的な内容をお届けします。
福祉を“たずねる”メディア──「こここ」の挑戦
最初に登壇したのは、マガジンハウス こここ編集部のプロデューサーである及川氏。マガジンハウスといえば、「POPEYE」や「Hanako」などライフスタイル誌のイメージが強いですが、「こここ」は単なる福祉専門メディアではなく、「福祉をたずねる(訪ねる・尋ねる)」メディアとしての独自性を持つと説明しました。
「こここ」の年間配信記事数は200本以上にのぼり、その活動は以下の2本柱で展開されています。
1.「こここメディア」
福祉の現場や専門家への取材を通じ、広義の福祉を伝えるメディア事業
2.「こここラボ」
マガジンハウスのネットワークを活用し、福祉と異業種を結びつけるプロジェクト参画
及川氏は、具体的な事例として、農林水産省の「日本農福連携事業」におけるセミナー企画や、福祉施設と建築家をつなぐ「みらいの福祉施設建築ミーティング」などを紹介。さらに、厚生労働省の「介護のしごと魅力発信等事業」においては、若年層への興味喚起を目的に以下の施策を展開しました。
● 「anan」「POPEYE」「こここ」で介護の特集記事を掲載、冊子としてイベント配布
● 介護の日にちなんだ「ケアするしごと展 by マガジンハウス」の開催
● 全国の介護・福祉現場を訪れる「ケアするしごとツアー」の実施
● 日本仕事百貨<しごとバー>合同企画「ケアするしごとバー」開催
● 小学生向け冊子「幸せに生きるって、どういうこと?知っておきたい介護のしくみと仕事」の制作
介護人材の不足という課題に対して「福祉・介護士のリアルを伝え、ポジティブな働き方やキャリアパスを知ってもらい、リアルな仕事の選択肢として捉えてもらう」ための施策だと及川氏は強調しました。

データ×マーケティングで介護の魅力を届ける──楽天グループの戦略
続いて、楽天グループの林氏が、デジタルマーケティングを活用した介護の魅力発信について語りました。
楽天グループの広報活動は、「サーロインの法則(作る:3、届ける:6、計測する:1)」に基づき、コンテンツをどうターゲットに届けるかに重点を置いています。楽天IDを活用し、ユーザーの行動ログを分析することで、「介護の仕事に就業する可能性が高い層」に最適な情報を届けることが可能です。
令和6年度の事業コンセプトは、「みんなの声が、かいごの未来をつくる。」 このコンセプトのもと、楽天は介護職の理解促進のためのポータルサイトを構築。100万PVを突破した「介護の仕事 魅力発信ポータル|知る。わかる。介護のしごと」では、以下のコンテンツを届けました。
● タレントのみやぞん氏・西川あやの氏を起用した「ON AIR KAIGOかいごのホンネ放送局」
● 漫画『左ききのエレン』とのタイアップ企画「左ききのエレン 番外編」
● 性別・年齢・年収別で検索できる介護の現場で働く現役職員の「みんなの声」
● 介護の現場で働く人やこれから介護職を目指す方々のインタビュー記事
また、楽天TVや楽天Koboでは介護関連の作品を無料公開、副業で介護職に従事する芸人やバンドマンを紹介する「tayorini by Lifull介護」タイアップ記事など、情報に触れる機会の創出・意識変容を目的とした施策を実施。
さらに、次年度以降の業界の活動に活かせるように、コンテンツに接触したユーザーを対象にしたアスキング調査も行われました。

教育を通じた意識変革──朝日新聞社の取り組み
最後に登壇したのは、朝日新聞社のオダカ氏。同社は「朝日小学生新聞」や「朝日中高生新聞」など、教育現場に強みを持つメディア企業として、次世代に介護の仕事を伝える取り組みを行っています。
令和6年度のプロジェクト名は「これからのKAIGO」。ターゲットは小中高生とその保護者・教員であり、次のような施策を実施しました。
● 全国から200件以上の応募があった「介護と私」作文コンクール
● 介護のキャリア教育をテーマに実施された教職員向けセミナー
● YouTubeチャンネル「ブカピ 部活ONE」での「全国高校生介護技術コンテスト」の密着動画配信
● 介護の必要性とお仕事を知る「出張授業」の全国8か所での実施
● 「おしごとはくぶつかん」を活用したデジタル教材の開発
これらの取り組みは、介護の仕事を身近に感じてもらう「ケアの心」を育む活動であるとオダカ氏はくり返し語りました。

介護の未来を変えるのは、「知ること」から
セッションの最後に、司会の小口氏は「介護のこと・福祉のことを知っていただくことで変わることがたくさんある」と述べ、「高齢者がわからない」小学生の存在や、介護よりも先に高齢者にサポートが必要な理由を説明しなければならない実態を伝えました。
本トークセッションを通じて「知ってもらうこと」の重要性が今一度明らかになりました。
● メディアの力で、介護のリアルを伝えるマガジンハウス・「こここ」
● データとデジタルの力で、適切な人に情報を届ける楽天グループ
● 教育の場を活用し、未来世代の意識を変える朝日新聞社
これらの取り組みが連携し、介護という仕事の魅力が正しく広まっていくことが、介護業界の未来を切り拓く鍵となるでしょう。
他セッション
「International KAiGO Festival 」とは
高齢化を脅威ではなく成長のチャンスと捉え、介護とシルバーエコノミーを変革
——KAiGOが日本と世界の未来を動かす答えと機会を生み出す場
3人に1人が65歳以上という急速な高齢化に直面している日本。介護職不足や約9兆円の経済損失などの課題を抱える一方、シルバーエコノミーは100兆円規模に成長する見込みです。「International KAiGO Festival」は、日本が世界に誇る介護の知見をさらに進化させ、介護を中心とした経済・社会のエコシステムを共創するプラットフォームとして立ち上げられました。スタートアップ、企業、政策立案者、投資家、介護職が集い、セッションやアワードを通じて次世代のビジネスモデルや技術革新を促進。「介護エコシステム」創出につながる業界を超えた価値ある学びが得られるインキュベーションの場として、日本と企業の未来を支援します。

「KAiGO PRiDE」とは
KAiGO PRiDEは、誰もが自分らしく安心して暮らせる社会の実現のため、クリエイティブの力で日本の介護を拡張・強化するプロジェクト。人類史に類をみない超高齢社会の日本では2040年に57万人の介護職が不足すると言われるなかで、私たちがライフクリエイターと呼ぶ全国の介護職・福祉職たちのSelf-respectを醸成し、社会からのリスペクトにつなげる「KAiGO-Branding」を展開。また、介護≠ケアとも言われ、私たちが世界一だと信じる日本の介護の持続可能性のため、様々なプレイヤーの巻き込みを図る「KAiGO-Ecosystem」の形成を推進しています。介護をKAiGOとして、その可能性と誇りをクリエイティブの力で形にするプラットフォームとして多様なプロジェクトをグローバルに展開しています。